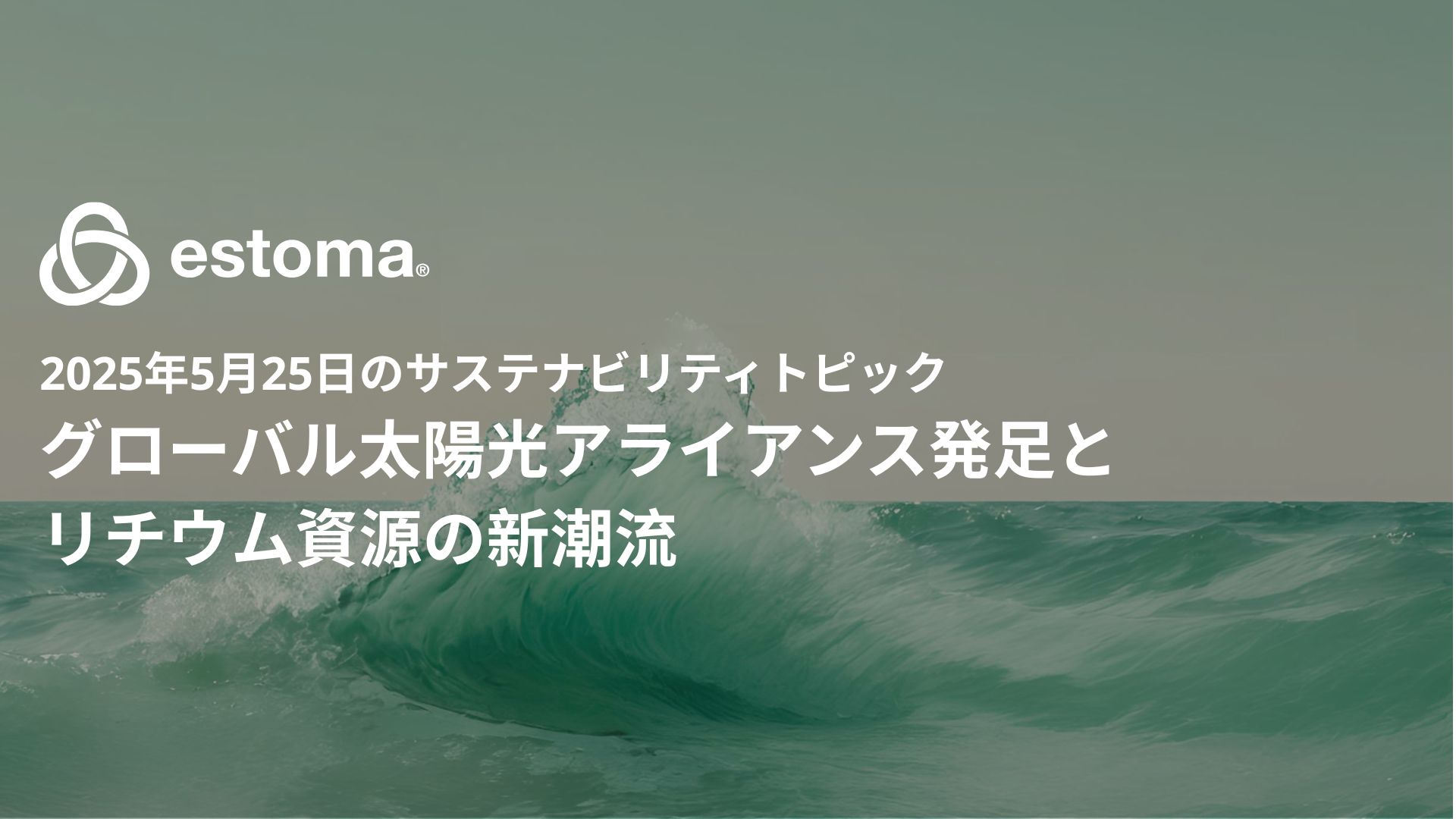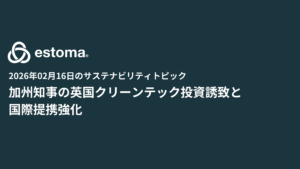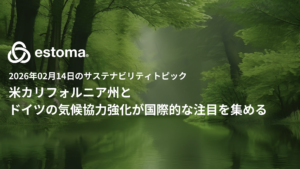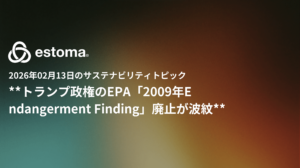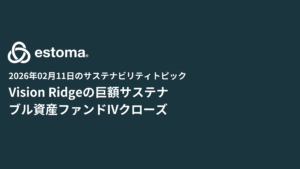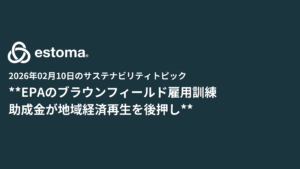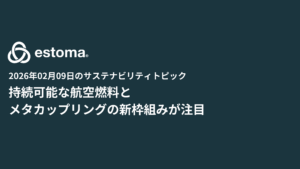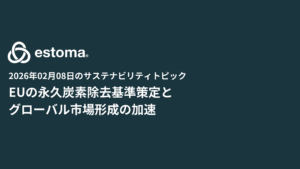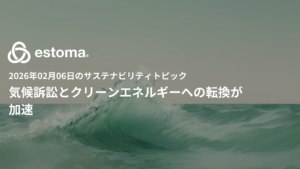2025年5月25日は、世界のサステナビリティ分野で注目すべき動きが複数見られた一日となりました。特に、国連グローバル・コンパクト(UNGC)主催のグローバル・ビジネス・サミットで発表された「グローバル太陽光持続可能性アライアンス(GSSA)」創設は、再生可能エネルギー業界全体に大きなインパクトを与えました。また、電気自動車(EV)産業を支えるリチウム資源への関心が高まる中、新たなレアアース革命を牽引する企業の動向も報じられています。本コラムでは、昨日投稿された最新記事やニュースリリースから、ESG担当者が押さえておくべき重要トピックを厳選してご紹介します。
昨日のサステナビリティ最新トピック
1. グローバル太陽光持続可能性アライアンス発足:再生可能エネルギー産業の新たな連携モデル
2025年5月25日、インドネシア・ジャカルタで開催された国連グローバル・コンパクト(UNGC)の初回グローバル・ビジネス・サミットにて、「JA Solar」をはじめとする世界24社の主要太陽光関連企業が共同で「Global Solar Sustainable Alliance(GSSA)」設立イニシアチブを発表しました。参加企業にはJinko SolarやTongweiなど中国系大手だけでなく、多様な地域からコア部材メーカーも名を連ねています。
このイニシアチブは、
– サプライチェーン全体にわたる環境配慮型鉱物調達
– 生態系および生物多様性保護
– 公平かつ包摂的な社会構築
– 持続的成長推進
など、多角的視点から再生可能エネルギー産業全体の持続可能性強化を目指すものです。各国政府や学術界とも協働しながら、「クリーンエネルギー普及」と「カーボンニュートラル実現」に向けて具体策実行へ踏み出した点が特筆されます。
2. リチウム:EV時代“液体ゴールド”争奪戦とレアメタル供給網変革への胎動
同日付の記事では、「Elektros Inc.」によるレポートとして、“現代版ゴールド”とも称されるリチウム資源への注目度上昇と、その供給網変革について取り上げられました。電気自動車バッテリー製造に不可欠なこの金属は、
– EV普及拡大による需要急増
– 価格高騰および安定調達競争激化
という状況下、新興プレイヤーによる採掘技術革新や環境負荷低減型プロセス導入など、“次世代型レアイース革命”とも呼ぶべき潮流が始まっています。
記事内ではイーロン・マスク氏による市場展望コメントにも触れつつ、「効率」「航続距離」「持続可能性」の観点から今後数年内にも劇的変化が起こり得ること、そのためにはESG観点からも責任ある鉱物調達基準策定や透明性確保が不可欠との指摘があります。
3. マレーシアイベント:観光×SDGs推進フェスティバル開催報告
また同日に公開されたまとめ記事では、マレーシアイベントとして26,000人以上来場した「持続可能ツーリズム推進フェスティバル」の成果について言及されています。このイベントは2026年訪問マレーシアイヤーへ向けてSDGs視点強化、市民参加型プログラム拡充等につながったとのことです。
(出典:https://www.winssolutions.org/sustainability-in-the-news-may-19–25–2025/)
まとめ
昨日(2025年5月25日)は、
1. 世界主要太陽光メーカー24社による「グローバル太陽光持続可能性同盟」創設という歴史的合意、
2. EV時代到来下で加速する“責任ある鉱物調達”競争、およびその先端事例紹介、
3. 東南アジアイベント事例として市民巻込み型SDGs施策拡充、
という三本柱で、大規模かつ多層的なサステナブル経営転換期到来を象徴する一日となりました。
特筆すべきは【再生エネ産業横断型ガバナンス強化】――単なる技術開発だけではなく、人権尊重/公正取引/自然共存まで含めた包括ガイドライン作りへ舵切りしたことであり、日本企業も今後こうした国際枠組み参画や情報開示高度化対応なしには競争力維持困難となっていくでしょう。
また原材料分野でも、“どこまで透明か”、“どこまで倫理的か”、という問い直し圧力はいっそう高まりそうです。