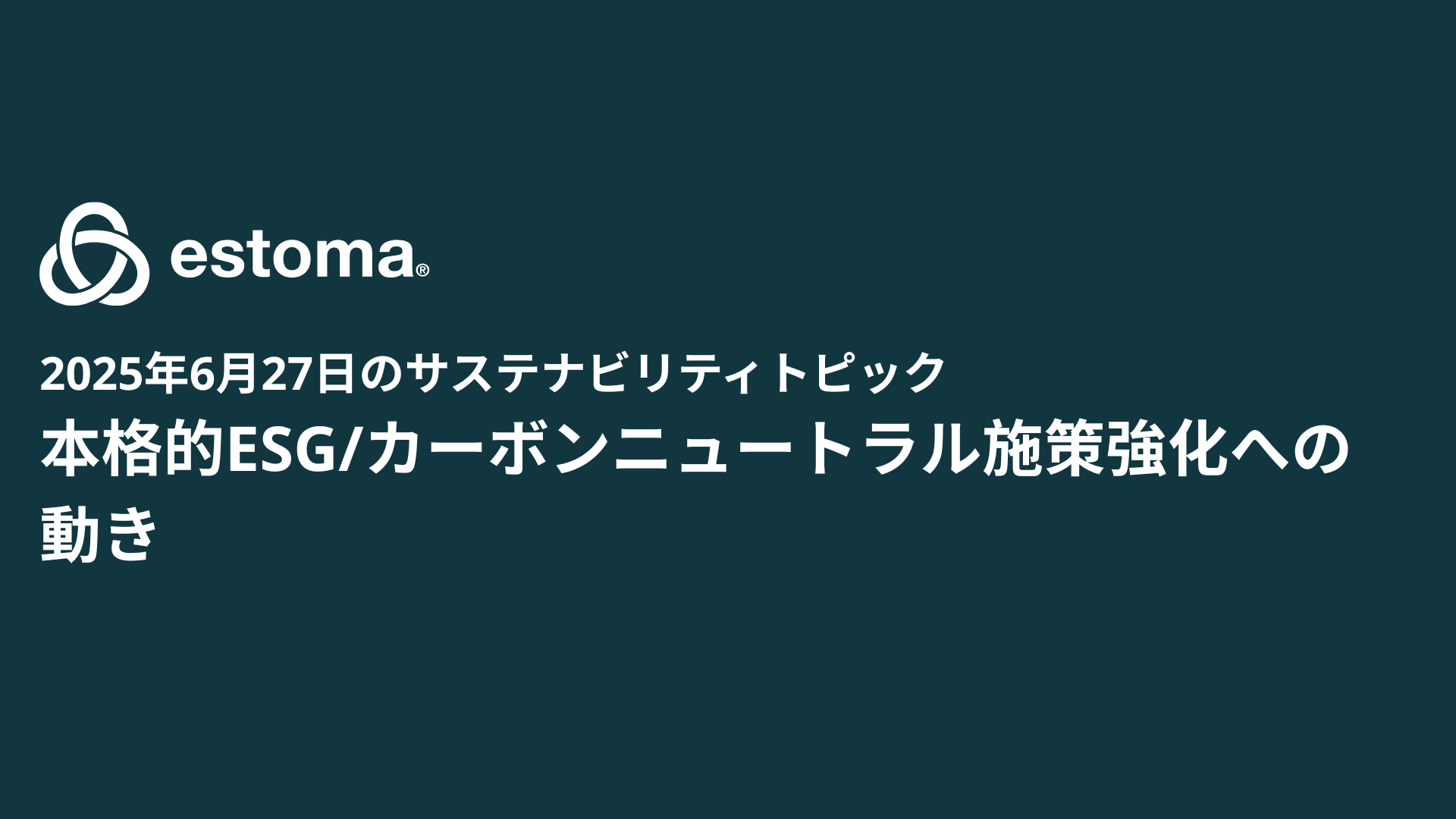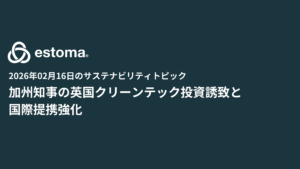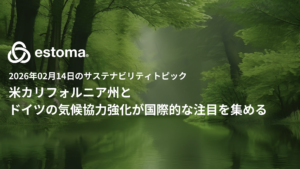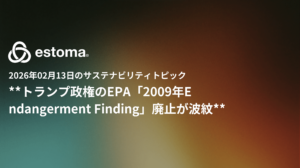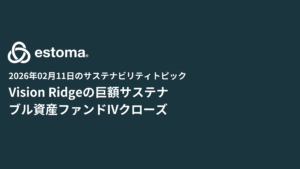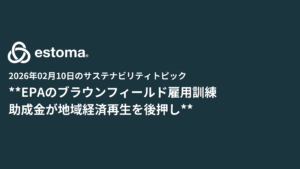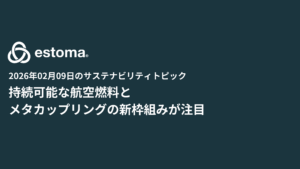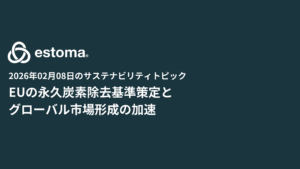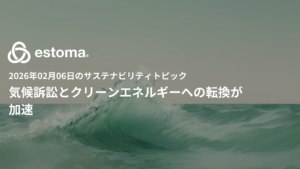2025年6月27日は、グローバル企業による新たなサステナビリティ戦略の発表や、ESG分野での最新レポート公開、大学による国際的な評価獲得など、多様な動きが見られました。特に注目すべきは、Samsung Electronicsが公表した「2025 サステナビリティレポート」と日立製作所の新しいサステナビリティ戦略「PLEDGES」の発表です。これらは今後の産業界全体に大きな影響を与える可能性があります。本コラムでは、昨日投稿された主要ニュース・論文を要約し、その動向と示唆について解説します。
昨日のサステナビリティ最新トピック
1. サムスン電子、「2025年版サステナビリティレポート」を公開
Samsung Electronicsは6月27日に「2025 サステナビリティレポート」を発表しました。同社はScope1および2排出量ネットゼロ達成への取り組みを加速しており、特にAI技術や関連産業の急成長を背景に再生可能エネルギー利用拡大と資源循環最大化へ注力しています。Device eXperience(DX)部門では再生可能エネルギー転換率93.4%(2024年末時点)を達成し、高効率エネルギー技術導入で2019年比31.5%の平均消費電力削減も実現。またプラスチック部品への再生材適用率31%、80カ国以上でe-waste回収プログラム展開など、多角的アプローチが特徴です。
(出典:https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-releases-2025-sustainability-report)
2. 日立製作所、新たなサステナビリティ戦略「PLEDGES」発表
日立製作所は同日、新しいグローバル・サステナビリティ戦略「PLEDGES」を公表しました。この戦略では気候変動対応だけでなく、人権尊重や多様性推進、公正なガバナンス強化など幅広いESG課題へのコミットメントが明確化されています。「PLEDGES」は今後の日立グループ全体として持続可能社会実現へ向けた指針となり、大規模イベント“Hitachi Social Innovation Forum 2025”でもその詳細が議論される予定です。
(出典:https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2025/06/250627.html)
3. PwC:AI時代と地政学的不安定下で問われる持続可能経営
PwC USによる6月27日のSustainability News Briefでは、「AI需要増大」「地政学的緊張」「気候変動による原材料供給不安」など複合的課題下で企業経営層が直面する意思決定について分析しています。特にコバルト等重要鉱物資源への熱ストレス・水不足影響や、それら供給網維持には循環型モデル移行・巨額投資(年間4.6兆ドル規模)が不可欠との指摘もありました。またデータセンター運用最適化事例等も紹介されています。
(出典:https://www.pwc.com/us/en/services/esg/sustainability-news-brief.html)
4. 米ペンシルベニア州:クリーン電力導入促進策検討
米ペンシルベニア州政府関係者は同日、新規電源プロジェクト認可手続きを迅速化するため専門委員会設置案を提示しました。同州では脱炭素社会構築と地域経済活性化両立へ向けて政策転換機運が高まっています。
(出典:https://www.alleghenyfront.org/episode-for-june-27-2025/)
5. テキサス大学アーリントン校:国際的SDGs評価獲得
テキサス大学アーリントン校(UTA)は健康・開発目標分野で世界的評価機関から高い評価を受けたことを報告しました。同校独自の教育研究活動や地域連携施策がSDGs推進モデルとして認知された形です。
(出典:https://www.uta.edu/news/news-releases/2025/06/27/uta-earns-global-recognition-for-sustainability)
まとめ
昨日(6月27日)は、大手グローバル企業による中長期視点からの本格的ESG/カーボンニュートラル施策強化宣言、およびそれら施策の遂行状況の報告というインパクトある情報開示が相次ぎました。
特筆すべき内容として挙げたいのは、「テクノロジーカンパニー主導による脱炭素×循環型社会構築加速」です。Samsung Electronicsの日次単位まで踏み込んだ省エネ成果報告や素材循環拡充方針(日用品メーカー顔負け)、そしてPwC分析にも見られるように“AI普及”という新潮流下でも揺らぐことないESG基準順守姿勢――これこそ今後数年間、日本企業含むあらゆる産業界プレイヤーにも求められるスタンダードとなっていくでしょう。
また一方で、公正かつ迅速な制度設計(米ペンシルベニア州)、教育研究機関主体となったSDGs推進事例(UTA)も着実に増えています。“トップダウン×ボトムアップ”双方からイノベーション創出圧力高まっている点にも留意すべきです。
総じて、「脱炭素」「資源循環」「人権尊重」――この3軸融合型イノベーションこそ、“次世代型競争優位”確保には不可欠と言えるでしょう。