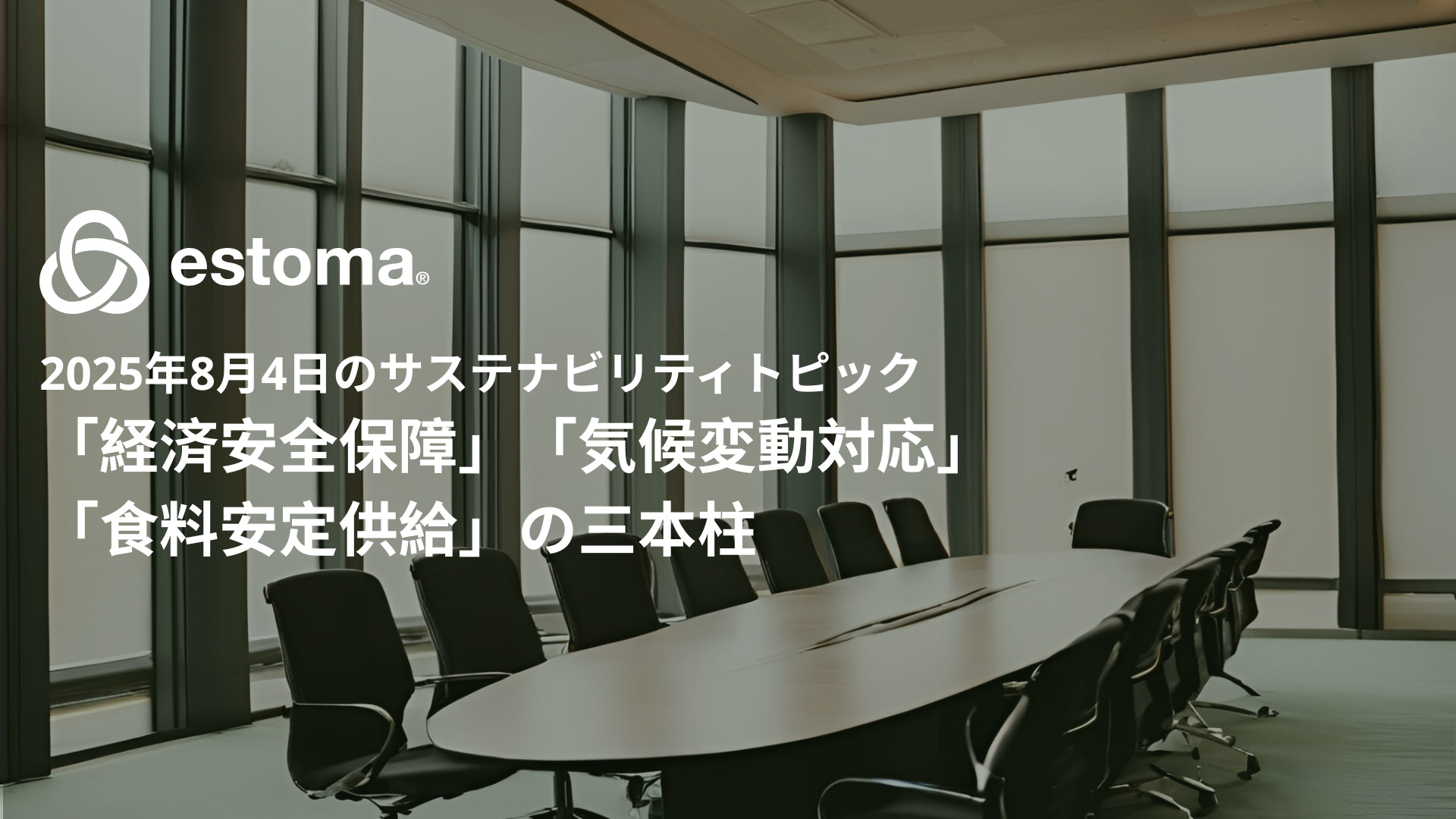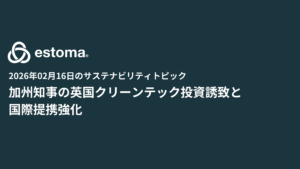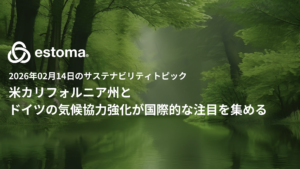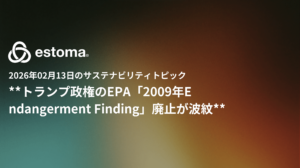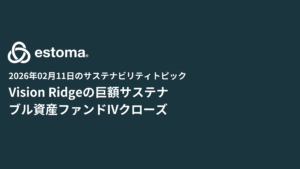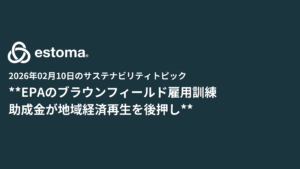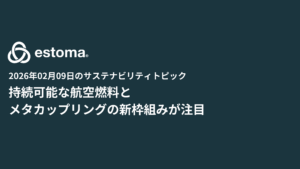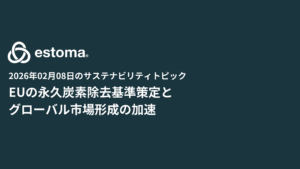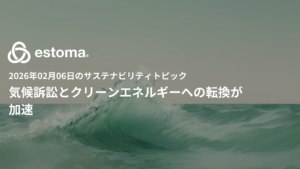2025年8月4日に発表されたサステナビリティ関連の最新ニュースや論文から、世界の政策動向、技術革新、社会課題への対応など、多角的な視点で注目すべきトピックを厳選しご紹介します。本日は特に「米国連邦エネルギー政策の大転換」と「持続可能な水産業推進法案」の2つが目玉情報です。グローバルな潮流とともに、日本企業が今後注視すべきポイントを解説します。
昨日のサステナビリティ最新トピック
1.米国連邦エネルギー・サステナビリティ政策:大規模転換と新たな分断
7月17日に米下院歳出委員会で可決された総額573億ドル(うち488億ドルはエネルギー省向け)の予算案を皮切りに、7月は米国連邦レベルでエネルギー・気候変動対策に関する大きな動きが相次ぎました。特筆すべきは7月4日に成立した「One Big Beautiful Bill(H.R.1)」です。この法案はインフレ抑制法(IRA)の主要部分を書き換え、「Energy Dominance Loan Program」を創設し、国内のエネルギー生産力強化と送電網信頼性向上へ舵を切りました。またAI・データセンター戦略も同時発表されており、インフラ整備促進や許認可手続緩和、人材育成加速などデジタル基盤強化にも重点が置かれています。
さらに国防総省による10億ドル規模のレアアース磁石供給網国内回帰プロジェクトや、中国製黒鉛への新関税導入も発表されました。FERC(連邦エネルギー規制委員会)、DOE(エネルギー省)、EPA(環境保護庁)では人事刷新も進行中であり、大統領選挙イヤーらしいダイナミズムと分断が鮮明になっています。今秋にはFY26予算審議や債務上限問題も控えており、更なる制度変更・投資機会拡大が見込まれます。
(出典: https://www.jdsupra.com/legalnews/energy-sustainability-washington-update-8424580/)
2. 米国:持続可能な水産業推進法案「MARA Act」提出
8月4日付で公表されたEDF (Environmental Defense Fund) の声明によれば、「MARA Act」が米上院に提出されました。同法案はオープンオーシャン養殖(水産養殖)について科学的知見拡充、安全性評価、地域社会との協調等を重視しつつ、その成長可能性と環境影響評価を体系的に検証するものです。海洋生態系保全、水産物供給安定化、および低炭素タンパク源としての役割強化という観点から、水産業界のみならず食品セクター全体への波及効果にも期待されています。
(出典: https://www.edf.org/media/bill-would-explore-responsible-growth-domestic-seafood)
3. ペンシルベニア州でのメタン排出規制延期巡る訴訟/AIデータセンター透明性要求/電力市場混乱
ペンシルベニア州ではEPAによる石油ガス部門メタン排出削減義務履行期限延長措置について、市民団体等から提訴されています。またAIデータセンター建設計画への透明性確保要請や天然ガス火力発電所信頼度低下によるPJM電力市場混乱など、多様な課題が浮上しています。一方、新たなリチウム抽出技術実証施設ツアー開催など脱炭素型素材開発でも前向きな動きがあります。
(出典: http://paenvironmentdaily.blogspot.com/2025/08/august-4-weekly-pa-environment-digest.html)
4. 2030年クリーンクッキング普及目標未達見通し/地球環境負荷超過日早まる傾向継続【参考】
IEA報告書によればサブサハラ・アフリカ地域では2030年までのクリーンクッキング普及目標達成困難となっており、新たに2040年へ先送りされました。その背景には資金不足・インフラ未整備・人口増加等複合要因があります。またGlobal Footprint Network によれば今年度地球環境負荷超過日は7月24日となり、人類活動圧力増大傾向が改めて示唆されています。(本項は8/3公開情報ですが補足として記載)
(出典: https://www.winssolutions.org/sustainability-news-july-15-august-4-2025/)
まとめ
昨日公表された記事群から読み取れる最大の特徴は、「経済安全保障」「気候変動対応」「食料安定供給」という三本柱それぞれについて各国政府主導型イニシアチブが一段と加速していることです。特筆すべきなのは米国連邦政府による包括的制度改革 – 従来型再生可能エネ支援策から自国内資源活用重視路線への転換、およびAI基盤整備との融合 – そして水産養殖分野でも科学根拠重視かつ慎重な姿勢ながら将来への展望構築へ踏み込んだ立法努力です。一方、市民社会側から行政手続きを巡る監督要求や訴訟提起も活発化しており、多様な主体間での対話なしには真の持続可能社会の実現につながらない現状も浮かび上がります。
日本企業として留意すべきポイント:
– グローバル調達網再編圧力
– AI×ESG領域投資機会
– サプライチェーン透明性確保義務
これらはいずれも今後数年間で競争優位構築あるいは喪失につながる重要なポイントです。