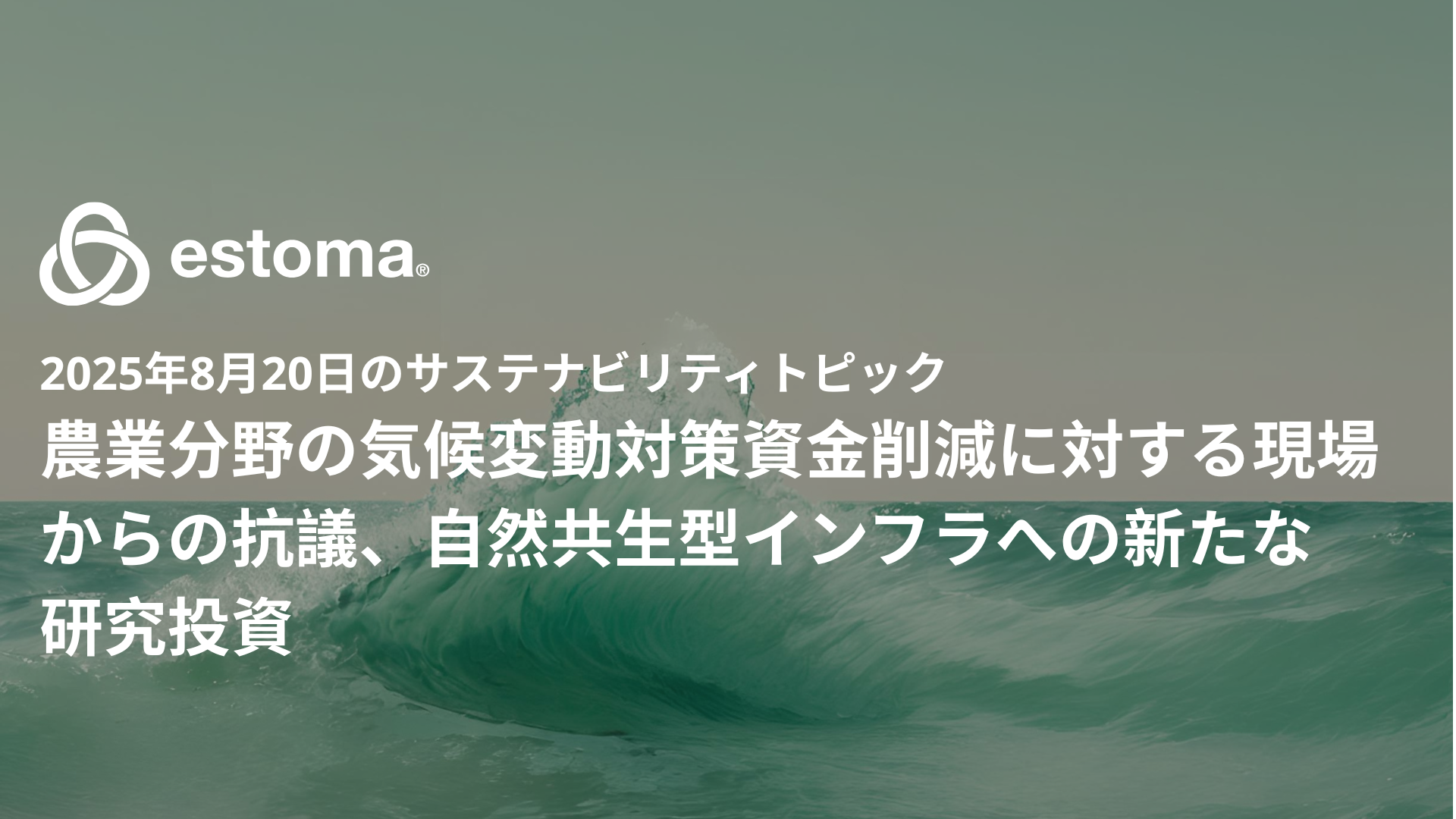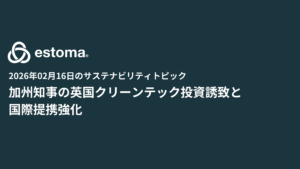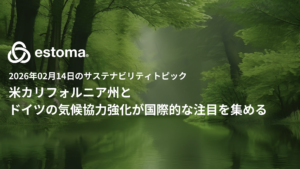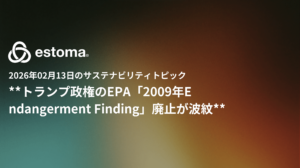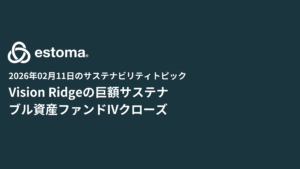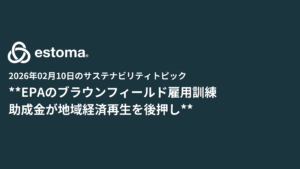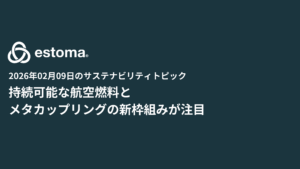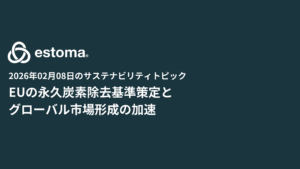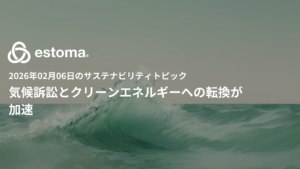2025年8月20日は、サステナビリティ分野で注目すべき複数の動きが見られました。特に米国では、農業分野における気候変動対策資金の削減を巡る現場からの強い反発や、「自然と共生するインフラ」への新たな研究投資など、持続可能性をめぐる政策・技術両面で重要なニュースが相次ぎました。本コラムでは、その中でも特筆すべき最新トピックを中心に、昨日投稿された海外専門記事・ニュースリリース等を要約し、ご紹介します。
昨日のサステナビリティ最新トピック
1. 米国ペンシルベニア州:農家による気候変動対策予算削減への抗議
2025年8月20日、ペンシルベニア州スクラントン地域で、小規模農家や環境団体が連携し、「気候スマート作物」など持続可能な農業支援プログラム(Partnerships for Climate-Smart Commodities)の連邦予算カットに抗議しました。
このプログラムは本来、小規模多様型農家による気候レジリエンス向上や保全活動推進を目的としていましたが、大規模企業型農場優遇へと方針転換され、中小規模事業者向け支援は打ち切りとなりました。
地元選出議員も「異常気象による2024年全米作物・牧草被害額は200億ドル超」と指摘しつつ、「最前線で危機対応している現場こそ支援強化が必要」と訴えています。
2. 自然共生型インフラ推進へ:オクラホマ大学、新たな大型研究助成獲得
同日発表されたオクラホマ大学エコシステム&流域研究所への300万ドル助成金決定も大きな話題となりました。このプロジェクトは「Building with Nature(自然とともにつくる)」という理念の下、
– 河川・貯水池・湿地等で自然由来/ハイブリッド型インフラ手法
– 空間的かつ時間的にも精緻化したデータ収集
– 実験およびモデリングによる効果検証
など、多角的アプローチで従来型社会基盤との比較評価を行います。
背景には「老朽化した既存インフラ更新期」に直面する米国内情勢があります。「従来通りか、それとも“より良い方法”=自然との協働か」という問い直しが政策論争として顕在化している点も特徴です。
(出典: http://ou.edu/news/articles/2025/august/unlocking-the-benefits-of-building-with-nature)
3. ハワイ州知事、新政策レポート公表:「人々のための成果」を掲げ環境保護施策強調
ハワイ州グリーン知事は8月20日付け新政策レポート『Results for our People』を公表しました。同報告書では、
– マウイ島山火事復興支援
– 違法銃器・農業犯罪抑止
– 医療人材確保施策
等幅広い課題解決戦略と並び、「環境保護」の優先度向上にも言及しています。
4. AI活用による個人向けエコ習慣促進アプリ開発:MyEcoPal登場
カリフォルニア州立サンタクララ大学チームはAI搭載モバイルアプリ「MyEcoPal」を開発。同ツールはユーザーごとの消費電力分析結果から、省エネ行動(LED照明導入や洗濯乾燥方法変更等)についてパーソナライズド提案を行う仕組みです。
過去数年間にわたり廃棄物管理学習×AI活用効果検証も実施済み。「知識→実践」のギャップ解消、および“毎日の小さな積み重ね”促進という観点から注目されています。
5. 環境NGOらEPA規制緩和案へ反対声明―仮想フォーラム開催
また同日にはEnvironmental Defense Fund (EDF) ほか多数市民団体主催によってEPA(米国環境保護庁)関連2件の重要規制緩和案撤回要求フォーラムも開催されました。健康被害防止および脱炭素社会構築加速へ、市民側から強い声が上げられています。
まとめ
昨日投稿された海外専門記事群を見る限り、
1. 公共セクター主導だった持続可能性関連予算配分について、“誰” を対象とするべきか – 特に中小零細主体 vs 大企業主体 – という根本論争が再燃しています。(例:米国スクラントン地域)
2. 老朽化社会基盤更新期 にあたり、“従来通り” の土木工学だけではなく、生態系サービス活用=Building with Nature 型手法への関心拡大、およびその科学的裏付けづくり投資増加傾向があります。(例:オクラホマ大学)
3. 個人生活領域でもAI技術応用 により、一人ひとりの日常行動変容促進ツール開発競争が始まっています。(例:MyEcoPal)
4. 行政トップ層レベルでも災害復興×環境配慮×産業振興一体設計志向 が鮮明になっています。(例:ハワイ州グリーン知事報告書)
これらはいずれも、日本国内外問わず今後ESG経営戦略立案時にも参考となります。