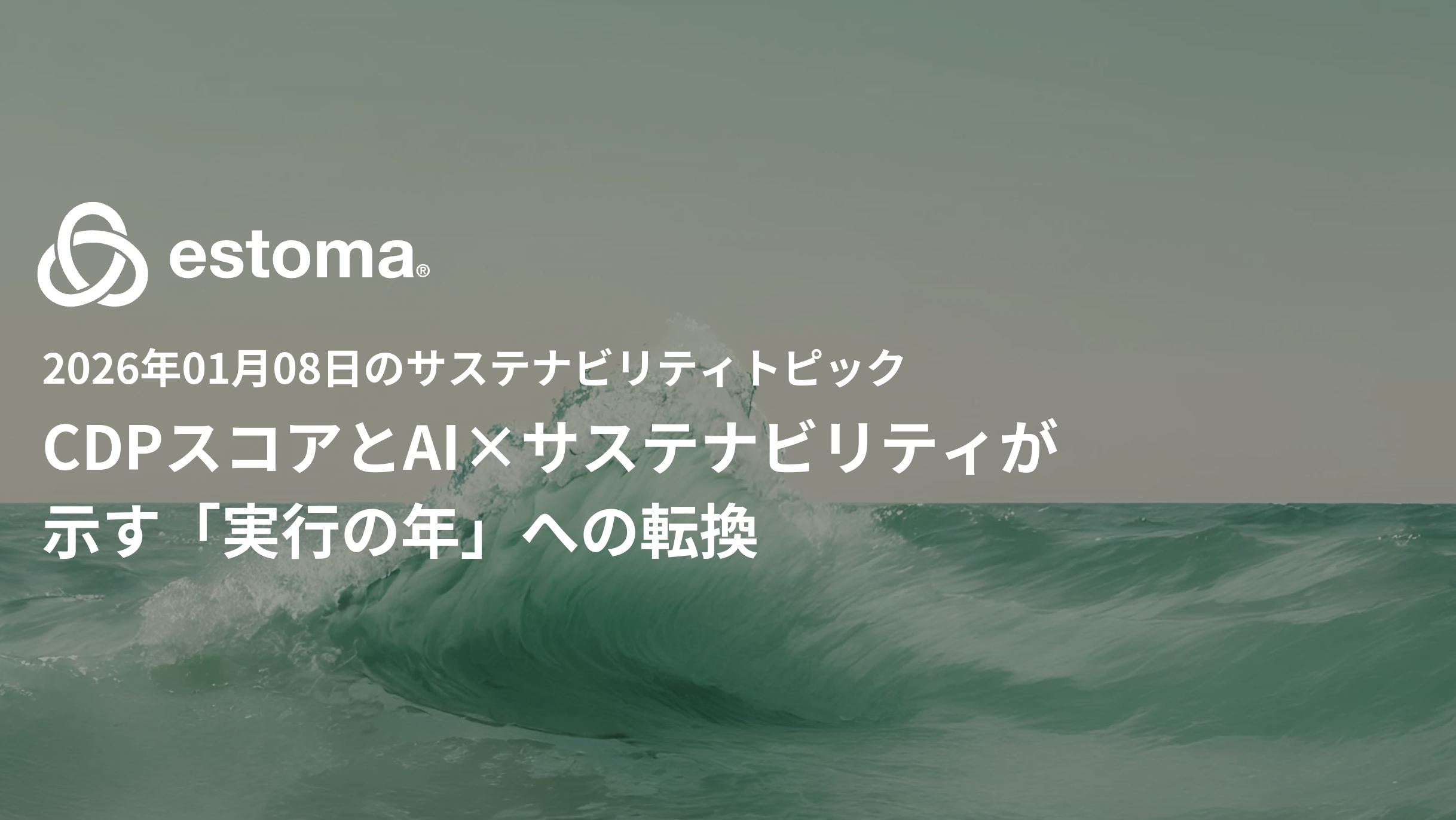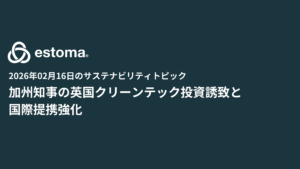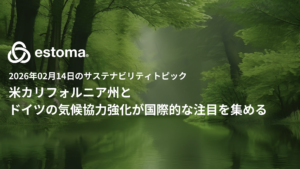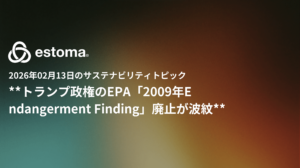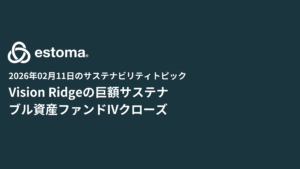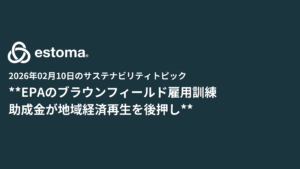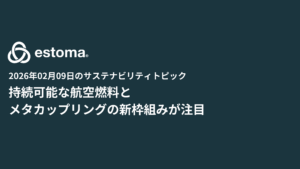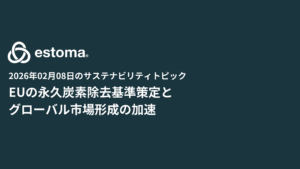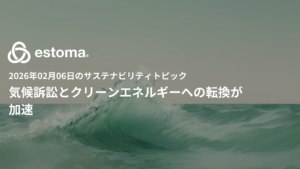2026年1月8日は、サステナビリティ分野で「評価指標」と「実装技術」の両輪に関わる動きが目立った一日でした。
特に、企業・都市のCDP評価に関する発表と、AIを活用したサステナビリティ実装に関する議論は、2026年を実行の年と位置づける流れを象徴しています。以下では、海外のニュースリリースや専門メディアを中心に、その概要と日本企業・サステナビリティ担当者への示唆を整理します。
昨日のサステナビリティ最新トピック
特筆して伝えたい内容(目玉)
「サステナビリティは公表するものから成果を出すものへ:
CDP評価におけるリーダーシップと、AIを組み込んだ実行フェーズへの移行が同時に進展」
- 朝日グループホールディングスと米国クリーブランド市が、CDPスコアにおいて最高評価の「A」ランクを獲得し、気候変動・水リスク対応の見える化とガバナンス水準の高さを示したこと。
- ITインフラ大手KyndrylのCSOインタビューで、「2026年は、グリーンウォッシュではなく実行と成果の年であるべき」と明言され、AIを活用した脱炭素・省エネの実装例が多数紹介されたこと。
企業のサステナ担当者にとっては、「CDP等の評価軸に沿った開示・戦略」と「AI等テクノロジーを組み込んだ実行力強化」が、2026年の優先テーマであることが改めて裏づけられた一日だったと言えます。
個別トピック要約(2026年1月8日付)
朝日グループ、CDP気候変動・水セキュリティでダブルA評価を獲得
東京発のニュースリリースによると、朝日グループホールディングス株式会社は、環境情報開示・評価機関であるCDPから、気候変動(Climate Change)と水セキュリティ(Water Security)の両分野で最高評価Aスコアを獲得し、「ダブルAリスト」に選定されたと発表しました。
これは、気候変動分野では2018年から8年連続、水セキュリティ分野では2年連続の「A」評価となります。
同社はグループ理念のもと、「2040年までにバリューチェーン全体でネットゼロGHG排出」を掲げており、この長期目標はScience Based Targets initiative(SBTi)によって検証済みとされています。温室効果ガス削減に加え、製造拠点の水使用に関する目標設定、水リスクを踏まえた流域レベルでのステークホルダー協働(水資源マネジメント)、なども取り組みの柱として強調されています。
示唆:
- 日本企業として、長期ネットゼロ目標+SBTi検証+CDPスコアという一連のフレームを揃えた好事例。
- 水リスクは「製造拠点内の効率化」にとどまらず、「流域・コミュニティとの協働」に踏み出している点が、CDPの評価軸とも整合。
- グローバルな投資家・金融機関に対し、「デカーボナイゼーション×水資源」の両面でリーダーシップを打ち出す日本企業としてのポジショニング強化につながる。
出典URL(テキスト):

クリーブランド市、CDPの都市向け評価で「Aリスト」に選定
米国・オハイオ州のクリーブランド市は、CDPの都市向け評価において、気候変動対応・環境レジリエンスに関する取り組みが評価され、CDPのAリストに選ばれたと発表しました。
同市は、CDP–ICLEI Trackプラットフォームを通じた環境データの公開、都市全体の温室効果ガスインベントリ整備、信頼性ある気候アクションプランの公表、気候リスク・脆弱性評価の実施、適応目標の設定など、CDPが定める厳格なリーダーシップ基準を満たしたとされています。
CDP CEOのコメントでは、「都市は、レジリエントでearth-positiveな未来を形作る決定的な役割を担う」とし、データに基づく透明性と包括的な気候計画が、コミュニティ保護と持続的成長の双方を実現しうることが強調されています。
クリーブランド市の環境・サステナ系施策としては、
- 温室効果ガス排出削減
- 再生可能エネルギー利用拡大
- 健康的な交通・建物の推進
- 廃棄物管理の改善
- 自然空間・街路樹へのアクセス拡大
など、多岐にわたるプロジェクトが掲げられています。
示唆:
- 都市・自治体レベルでも、CDPを通じたデータ開示+気候計画+レジリエンス戦略が「先進事例」の条件になりつつある。
- 金融機関はCDPデータを、投融資判断・債券発行(例:グリーンボンド・サステナビリティボンド)にも活用しており、都市のCDPスコア向上は、資本アクセスの観点でのメリットが期待される。
- 日本の自治体にも、TCFD/ISSB連動の気候情報開示と、CDP等を通じた国際的な「見える化」戦略が今後より重要になる。
出典URL(テキスト):

「2026年はグリーンウォッシュではなく実行の年に」:AI×サステナビリティの行方(Kyndryl CSOインタビュー)
アイルランドのテックメディアSilicon Republicは、ITインフラサービス大手Kyndrylのチーフ・サステナビリティ・オフィサー(CSO)であるFaith Taylor氏へのインタビュー記事を掲載し、AIとサステナビリティの関係、および2026年のテクノロジー起点のサステナビリティ動向について分析しています。
同社が公表した「Global Sustainability Barometer 2025」の結果によれば、
- 調査対象1,286社のうち、66%が環境目標およびプログラム実行を維持または強化した一方、35%は環境への取り組みを減速させたとされています。
- AI導入を進める企業の中で、「AI活用の環境インパクト」を考慮する企業の比率は、前年の35%から43%に増加したものの、IT・AIを脱炭素や環境負荷低減に本格統合している企業は21%にとどまると報告されています。
Taylor氏は、「AIは環境フレームワークの中核に位置づつつあり、エネルギー使用の監視や予測などで実際に使われている」とした上で、以下のようなユースケースを挙げています。
- 予知保全:設備の寿命延長・廃棄削減
- スマートグリッド最適化:再エネの統合と電力効率化
- 交通分野のルート最適化:燃料消費削減
- 建物のインテリジェントシステム:エネルギー使用の削減
一方で、AI自体のエネルギー消費・カーボンフットプリントも課題であり、
- AIシステムの全ライフサイクルにおける炭素影響評価
- クリーン電源の活用
- ワークロードの効率的な最適化
など、「環境効率を意識したAI設計」が必要と指摘しています。
記事後半では、2026年の見通しとして、
- 多くの企業がコンプライアンス起点からプロアクティブな、AI支援の環境戦略へと移行しつつあること。
- 持続可能性目標をビジネス成果(ROI、新規売上)とリンクさせている企業ほど進捗が早く、2026年はその差がより鮮明になる可能性があること。
- Scope 3削減も含め、ビジネスモデル自体を再設計するレベルでAI活用が進む「転換点(tipping point)」になりうること。
が強調されました。
示唆:
- AI=環境負荷の加算要因という懸念だけでなく、AI=サステナ戦略の実行エンジンとしての側面が、実例を伴って広がりつつある。
- それでも「きちんと環境に統合できている企業はまだ2割強」であり、2026年は「先行組」と「追随組」の差が開く年になりうる。
- 日本企業としては、エネルギー管理、サプライチェーン物流、設備保全、ビルマネジメント等の領域で、AIを組み込んだサステナビリティ・アーキテクチャの構築が重要な経営アジェンダになる。
出典URL(テキスト):

(参考)その他、1月8日前後の環境・サステナ関連情報
1月8日付として検索される情報の中には、以下のような政策・法務・環境規制動向の総括記事も確認されましたが、いずれも広義の「環境・エネルギー」枠に含まれるものの、ピンポイントな「サステナビリティの最新トレンド」というよりは、アメリカの予算・規制などをまとめた技術的・法務的なノートに近いため、本コラムでは詳細な要約は割愛します。
- 米法律事務所による「Environmental Notes – January 2026」(2026年1月8日付)など、規制・コンプライアンス動向の専門メモ。
サステナ担当者としては、TCFD・ISSB・CDPに加えて、各国・各州の規制・訴訟リスクを把握するうえで有用な情報源となりえます。
出典URL(テキスト):

コラムのまとめ:2026年のキーワードは「評価」と「実行」の両立
2026年1月8日に発信されたサステナビリティ関連のニュース・記事を俯瞰すると、次の3つのメッセージが浮かび上がります。
1. 評価指標としてのCDPの存在感が一段と強まっている
- 朝日グループのダブルA、クリーブランド市のAリスト入りは、企業・自治体ともに、CDPを通じた透明性+戦略性+実行度の証明が国際的な「通貨」になりつつあることを示しています。
- 日本企業・自治体にとって、CDP・ISSB・SBTiなど国際的な枠組みと、自社(自自治体)の実務をどう結びつけるかが、今後ますます重要になります。
2. AIは、サステナ戦略を「設計する」だけでなく「動かす」ための基盤へ
- KyndrylのBarometerとCSOインタビューからは、AIのユースケースが、エネルギー、設備、物流、ビルなど多方面で具体化している様子がうかがえます。
- 一方で、「環境負荷の高いAI」リスクも同時に意識されており、環境効率を組み込んだAIアーキテクチャ設計という新たな課題も提示されています。
3. 2026年はDelivery, not Greenwashingの年
- 「2026年は、グリーンウォッシュではなく『実行と成果の年』にすべきだ」というメッセージは、単なるキャッチフレーズではなく、CDPスコアやROIで測定される世界が定着しつつあることの表現と解釈できます。
- 日本のサステナビリティ担当者にとっても、
- 目標や方針の公表(ディスクロージャー)
- 評価機関や投資家が活用できるデータ整備(アカウンタビリティ)
- AI等を活用したオペレーション改善・ビジネスモデル変革(実行・成果)
の三層を、ストーリーとして一貫しているかという視点で見直すタイミングと言えるでしょう。
本日の示唆としての一言:
「2026年、サステナビリティは評価されるものから、テクノロジーで動かし、成果を証明するものへ。CDPとAIの動きを、自社戦略の見直しにどう組み込むかが問われる。」
社内の経営層・関連部門との対話や、次期サステナビリティ戦略・中期経営計画の議論にあたって、本コラムが一助となれば幸いです。